父母のめぐみ(父母恩重経のはなし)


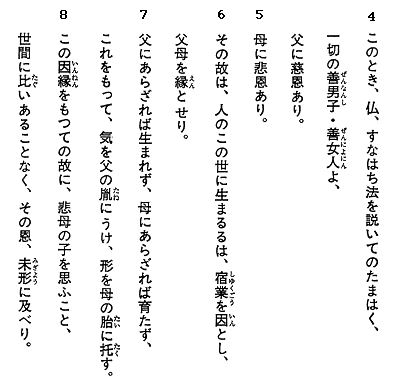
|
4 このとき、仏さまは父母の恩のめぐみについての教えをお説きになりました。 信仰のあついすぐれた人たちよ、 父には慈恩があります。 5 母には悲恩がります。 6 そのわけは、誰でもこの世に生まれてくるのには宿業を因とし、父母を縁としています。 7 もしも父がいなかったならば、この世には生まれてこなかったはずであり、母がいなかったならば育たなかったわけであります。このようなわけで、心は父親から直接うけ、形は母親からいただいたものにほかなりません。 8 こうした因縁をもっているのですから、悲母がわが子を思うのは世間のどんなものにも比べものになりません。そして、その恩はまだ子がこの世に生まれてくる前に及ぶのであります。
お釈迦さまはそこに集まってきた者たちが、一人残らず孝心ふかく心清らかなのを見そなわしたのでありましょう。そこで、まさにこのとき父母の恩のめぐみが何ものにもかえがたく尊いことをお説きになったのでした。 「善男子・善女人(ぜんなんし・ぜんにょにん)」とは、信仰心のあつい立派な男女です。
「父に慈恩あり、母に悲恩あり」、について
「慈恩、悲恩」、「父母恩重経」の『恩』という言葉について
このお経では、父性愛を「慈」、母性愛を「悲」といって、はっきりと使いわけています。 「慈」はいつくしみいたわる愛であります。 父性愛は、わが子をじっと見つめている愛、いわば精神的な愛ともいうべきであります。 そうした父性愛のはたらきが「慈恩」です。
「悲」はかなしみいたむ愛であります。 母性愛は、身をもってわが子を抱きしめ守る愛、いわば感性的なともいうべきでありましょう。 そうした母性愛のはたらきが「悲恩」です。
仏教でいう恩はインドのサンスクリット語の「ウパカーラ」の訳語であります。 その意味は「近くにつくること、あるいは近くになすこと」という意味で、 自分の近くにあってはたらきかけるものというのでありますから、 自分じしんをとりまいているところのありとあらゆるものによって自分が生かされていることを思えば、すべては恩の一語で、それを受けとめることができるはずであります。 恩という漢字をみると因と心とから成っており、因が音を示すといわれます。 心の因、つまり、心のよるところ、心のたよりとするところという意味ですから、結果的には恩のめぐみを与える主体をさす原語「ウパカーラ」と同義になります。
なお、仏教では「慈悲」といえば、本来、仏さまの限りなく深い、絶対の愛をさしています。 しかしインドでは「慈」を「メッター」、「悲」を「カルナー」と使いわけています。
「人のこの世に生まるるは、宿業を因とし、父母を縁とせり」、について
「人のこの世に生まるるは、宿業を因とし、父母を縁とせり」、について
このごろの若い人たちのなかには、頼みもしないのに生んでくれたとか、生まれてこなければよかった、などと平気で口にする者もいます。 この世に生まれて来たいと思って生まれたひとは一人もありませんし、また生まれて来たくまかったが仕方なしに生まれてしまったというひともありません。 好むと好まざるとにかかわらず、生まれて来て、現にこうして生きているのは厳然たる事実であって、これ以上、確かなことはありません。 自分が自分だと気がついたときには、すでに自分は生きているのであって、これ以外にどうすることもできません。
「人のこの世に生まるるは、宿業を因とし、父母を縁とせり」、について
「宿業」とは、無限の過去世から積み重ねられてきた業、すなわち行為であります。 父母にはそれぞれ父母があり、三代前には8人、四代前には16人の父母がいたことになります。 それはちょうど逆三角形のように上方にむかって限りなく開いており、その逆頂点にこの私じしんが立っているわけであります。 こうして生命の始源と直結しているのが、この私であります。この生命の流れはたとえていえば、 目に見えない内なる大いなる河の流れのようなものです。 もしも過去のあるときに、この流れが断ち切られてしまったならば、むろん、現在の私じしんの存在があろうはずもありません。そういうことを考えてみますと、宿業を因としという教えが、いくぶんかは分かるような気がします。
父母の恩のめぐみには当然のことながら先祖の恩がふくまれていることを忘れてはならないと思います。
ひとくちに因縁といいますが、厳密にいうと因と縁とは区別されます。 因は原因、縁は福次的な原因、つまり条件であります。 生命の流れともいうべき直接原因があったところで、父母という補縁がなかったならば、この私は生まれてこなかったことはいうまでもありません。 父にあらざれば生まれず、母にあらざれば育たず、とあるとおりであります。
「気を父の胤(たね)にうけ、形を母の胎(たい)に托す」、について
父母からどういう恩のめぐみを受けたかということを具体的に示されたものであります。 精神的なものは、父からそのもとをいただいたものだというのです。 肉体的なものは、むろん母胎において養われたものであります。 私たちの生命が母胎のなかで次第に形をなしつつあったときのことを想像してみますと、人間の意識がおよぶ限りの範囲というものが、いかにせまく小さいものかがはっきりします。 無意識の世界、私たちの思慮分別のはたらかないところで、この私の誕生は準備されてきたわけであります。
「その恩、未形(みぎょう)に及べり」、について
いまだ形をさない以前から恩のめぐみを受けているというのは、お釈迦さまの深い思いめぐらしによる尊い教えであります。 ところで、みずからの意志で生まれてきたのではないのと同じように、欲するといなとにかかわらず、敢えてみずからの意志に反してでも死んでゆかねばなりません。 仏教のほうでは定命(じょうみょう)ということをいいます。 つまり生まれ落ちるとともに、そのひとの一生の寿命はほぼ決定しているというわけであります。
生きる意志は確かにはたらいていますが、それは生の実相の半面にすぎないのであって、その見えざる半面は生かされている命だということであります。 生かされている命に気づくのは宗教的な自覚にそのまま繋がっています。
どんなに生命尊重を叫び、人命の尊厳を説いたところで、各人が「授かった命」という自覚と感謝の念をもたない限りはどうしようもありません。「授かった命」という自覚と感謝の念は、 「その恩、未形(みぎょう)に及べり」というお釈迦さまのお諭しをよくよく思いめぐらすならば、ゆうぜんとわき起こってくるはずであります。
さて、人のこの世に生まるるは、、、で、 「頼みもしないのに生んでくれたとか、生まれてこなければよかった」、 というセリフ、聖書(旧約聖書)にもそういうことを戒めている箇所があります。
イザヤ書 45:10ああ、わざわいなり、
なぜ子をもうけるのか、と父親に言い
なぜ産みの苦しみをするのか、と女に問う者は。
父親、母親に向かってこのように言うことは大罪です。 十戒の中の一つ「親を尊敬せよ」に違反しています。 もう一箇所を紹介します。
ヨブ記 3:1〜ヨブは、決して、自分の親に向かってこのように言ったのではなく、 神に対して文句を言っているわけで、「親を尊敬せよ」には違反してはいないと思います。 ただ、ヨブは自分の正義を主張する勢いで、神を侮辱しているとも言えますが。やがてヨブは口を開き、自分の生まれた日を呪って、言った。
わたしの生まれた日は消えうせよ。
:
なぜ、わたしは母の胎にいるうちに死んでしまわなかったのか。 せめて、生まれてすぐに息絶えなかったのか。

もう一つ、中世の文学作品の中から、関連した言葉を引用しておきます。おわりミルトス作「Paradise Lost(失楽園)」の第十巻目には、 神の禁じた知恵の実を食べてしまったアダムが、それを後悔して自問自答をする場面があります。
私のあとに続いて代々生まれてくる者は一人残らず、私のためにもたらされた禍を怒り、 私を呪うにきまっている。 そして、「われわれのよごれた先祖に禍あれ! われわれのこのざまはアダムのせいなのだ、 彼に感謝を捧げようではないか!」と言うであろう。 この感謝が呪いの意であることは勿論だ。 自分自身につきまとう呪いの他に、 私が原因で生ずる子孫のすべての呪いも、 恐ろしい力で私に跳ね返ってこよう。
:
主よ、なぜそれ以上に、果てしなき苦しみをさらにつけ加えようとなされるのでしょうか。 (主はこうい言われるであろう)アダムよ、お前は条件を承諾したはずだ。 お前は善きものを享受し、そのくせ後になって条件に文句をつけようというのか。 神はお前には無断でお前を造ったかもしれぬが、もしお前の息子が親であるお前に逆らい、 叱られ、お前に向かって「なぜ俺を生んだのだ、俺は頼みはしなかったはずだ」と、 口答えしたらどうなる。 親に対する侮辱をごまかす、こういう言い訳をお前は認めるのか。 お前の子はお前の選択によってではなく、自然の必然によって生まれたはずだ。
:
 Top of 父母恩重経
Top of 父母恩重経