|
まず、個々の事象を紹介する前に、アイルランドという国の歴史的構造を見てみる。
するとそれ自体が大きなカラクリにあてはまるような錯覚すら覚える。
というのも、アイルランド史の中でケルト文化というのは
その重要なほとんどの部分を占めるとはいえそれが「すべて」ではないからだ。
ケルト人たちがその文化を引っさげてアイルランドに渡ってきたのは
紀元前200年ごろだと推定されている。
だが、それ以前にもアイルランドには歴史があるし、一方のケルトも地域を
アイルランドに限定しない広い範囲で栄華を誇っていた。
いわば「時間」と「空間」の軸がそれぞれ別に進行していったというわけ。
そしてアイルランドはケルトの終末の地であるわけだ。
一度は制圧したローマ軍に逆転され追いやられたその最果ての地が
アイルランド(スコットランド・ウェールズ・ブルターニュ)なのである。
そしてケルト以前の歴史については大まかに3つに分けられる。
1.ほとんど解明されていない中石器時代(紀元前6000年頃〜)、
2.ニューグレンジ遺跡に見られる石塚の建設が行われただろう共同体が
存在した時代(紀元前3000年頃〜)
3.金属器を作る技術を持っていた人々が渡来した青銅器時代(紀元前2000年頃〜)
巨大なストーンサークルを作り、そこで宗教的儀式を行っていたらしいと推定される。
その後、紀元前200年頃に鉄器文化を携えケルト人が2派に別れてアイルランドに渡来する。
そして先史時代に残された「渦巻模様」を巧みに取り入れたケルト文化を
のちのち花開かせてゆく。
この「巨石文化」以前とケルト文化との断層がまず謎である。
(もちろん巨石文化自体、大いなる謎なのだが)
そして「ケルト」そのものにも数々の伝説が残されている。
文字を持たなかったために明確には分からない、しかし数々の遺跡から推測される
(またはローマ軍に代表される他文化から描写されるところの)彼らの種族像が
これまた異色である。
ここではその彼らの文化について記してゆくことになるのだが
それらには少なからず先史時代もその影を落としている。
巨石文化はケルトが生み出したものではないが、両者が出会ったのは偶然か否か?
そんなことを感じさせる辺境の地がアイルランドなのである。
異界を信じ、共存した人々とはどんな精神構造を持っていたのだろうか。
それともアイルランドという地が彼らをそう変容させたのだろうか。
すべては想像するしかないのだ。
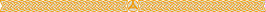
前述のごとく、ケルト人は「文字で記録すること」をしなかった。
そこで彼らのことはギリシア・ローマ人の記録から間接的に知るしかない。
それらには主観(偏見)が入ることは否めないが、戦争・商業的交流があったことから
伝説・神話とは一線を画す信頼性があるという。
代表的なのはユリウス・カサエル「ガリア戦記」、歴史家ストラボン「地理誌」、
政治家プリニウス「博物誌」などである。
「ガリア人は考える。人の命を救うには、ほかの命を捧げて神々の怒りを鎮めるしかない。そこで、定期的に生け贄の儀式が行われる。部族によっては途方もなく大きい人形を木の枝で編み、そこに生きた人間を詰め込み火にかける。そうして中の者たちを焼き殺してしまうのだ。」
(ユリウス・カサエル「ガリア戦記」)
「人身御供には他にもいろいろなやり方があった。たとえば弓で射殺す。神殿で串刺しにする。生け贄を後ろから短剣で突き殺す。このとき犠牲者が身悶えするのを見て、未来を占うことも行われた。」
(ストラボン「地理誌」)
さて、ケルト文化の象徴ともいうべきなのがドルイドという存在だ。
意味的には「大いなる知恵者」なのだそうだが、圧倒的な権力を持っていたという。
さまざまな「秘儀」を行ったというが、その儀式は「月の満ち欠け」と関係していたらしい。
祭祀の中でも最も特異なものは「首狩り」で、ケルトにとって人間の頭部は神聖視されていた。
頭は霊魂の宿る場所だったのである。
こうした信仰はなにもケルトに限ったことではないが、しかし他にもまして熱心に行ったという。
ケルトの異教はのちにキリスト教伝来により見事な融合を遂げるが
それにはイエスの起こした数々の奇跡が大きな要素を占めるほか、ケルトの半神半人の英雄に
通じる大きな共通点があった。
それは尋常でない出生のいきさつ。(イエスは処女懐胎)
聖書に書かれていたことはケルト人にとっては古代の伝説そのものであったのだ。
そして最後は十字架の受難。
その姿は伝説の勇者たちに重なる。
アイルランドがガリアと呼ばれていた頃の英雄たちはみな
栄光に包まれて若死にすることを望み、平凡に生き長らえることを拒絶する。
そしてこの信念は遠い時を隔て現代にまで及ぶ。
いわゆるイースター蜂起〜IRAまで…ナショナリストとして発言するパトリック・ピアスは
その信奉者たちに説いた。
「短くても栄光に包まれて死にたい。屈辱の生をただ長らえるよりは。
我が人生が一日と一夜だけの運命であっても構わない。我が名と勲功が死後も残るならば」と。
内戦の露と消えたマイケル・コリンズなど、ケルトの英雄そのものである。
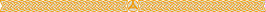
…と、ここまで書き進めてきて急に不安になってきたのだが
書き手である私にはケルトに対するイメージがすでにあり、それに対する
理想と現実も知ってしまっていて、その上でのこれはいわば「お遊び」であるのに
受け手側にはたしてそのあたりのことをどう伝わるだろうかと。
実際、ヨーロッパやアメリカなどではケルトを神聖視している部分
(ロマンティックに捉えているというか)があり、そういう土壌がしばしば
詐欺まがいの事件も起こっている。(マクファーソンやヨーロの愚行については
またいずれ…ケルトにある種のロマンを感じている人々の弱みといおうか
それを巧みに利用しペテンにかけたのだ)
そんな意図的なミスリードは論外としても、空想と現実の区別がつかない人というのは
現代に限らず存在したのだから、現在もこの先も自らワナをかけてそこにはまるというような
過ちを犯さずにいてくれることを祈るだけである。
(なぜならどんなに細心の注意を払っていても読み誤る人はいるものだ)
ただし、そうはいってもやはりケルトは充分にロマンティックなのだ。
残酷さとエロティシズムに彩られる、刺激好きな、何よりも自由を求めた気性。
それがすなわちケルトである。
それゆえ、枠にはまらない想像力あふれた物語に「ケルト的」なものを感じるのである。
しかしここに書き連ねているケルトの逸話とて、許せてもおそらくすべてを
受け入れることは困難だ。(たとえば「肉体は単なる入れ物である」といったような
「死」というものの捉え方等)
そういう考えを「ゆるす」と「認める」という間には大きな隔たりがあるのだ。
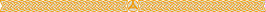
最初に記したように、ケルトとストーンヘンジ群とは直接の関わりはない。
ニューグレンジに残る「渦巻模様」もケルトが生み出したものではない。
ケルトはそれら古代の遺跡を自らの文化として積極的に取り入れ融合させていった。
これがいかなる理由からかは想像するしかない。
なにせストーンヘンジからして誰が何のために作ったのか謎なのである。
ケルト民族にとっても、それは大いなる謎だったに違いない。
そして自らの血がそうさせたのか、それとも何か外部からの霊感めいたものがあったのか
まるで連綿と続くひとつの事象のごとく自然に混ざり合っていった石の文化に
やはりひとつの「力」を感じる。(運命ともいうか)
石はケルトのために用意されていたのでは?とすら…。
石がケルトに何らかの力を与えたのは間違いない。
インスピレーションを引き起こし、多くの伝説が生まれるのに大いに役立ったことだろう。
それらは今の私たちが見ても充分に神秘的なのだから。
その神秘性を増幅させていったのがドルイドに代表される存在であるのだが
これは単に戦略上の役割分担だったのか、それとも何か天啓があってのこのなのだろうか。
想像力に長けた民族の中でも最もその力の強い者が極めていった結果なのかも知れない。
(ケルトのこの柔軟性はやがてキリスト教伝来と共に駆逐されながらも
またもや融合してその最期ともいうべき花を咲かせた。
幻想と抽象、闇と生命力のカオスと呼ばれる装飾写本として集大成されたのだ。
この世紀のベストセラーを絢爛かつイキイキと鮮やかに彩ったことで
民族の存在は永遠に記憶されるだろう。)
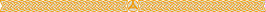
ところでドルイドは本当に今でいう「超能力者」のようなものだったのだろうか?
彼らの信仰に基づく所為はまさしく神秘のオンパレードなのだが
はたして本当に常人以上の何かをなしえたのであろうか??
残念ながらそういった見聞録はない。
あるのはドルイドを取り巻いていた奇怪な描写だけである。
ケルト人は樹木を、中でも樫の木と寄生木を神聖視していた。
「彼ら(ドルイド)は樫の木に生えるものはすべて天から贈られたのであり、この木を神が選んだと考えている。しかし寄生木が樫の木に生えることは稀で、見つけると盛大な儀式を催して刈り集める。それは特に月の第6日、および一世代の30年が過ぎた後に行われる。
寄生木はガリアの言葉で「すべてを癒すもの」と呼ばれる。
白い服を着た僧侶が木に登り、黄金の鎌で寄生木を切り落とし、それを白い外套で受け取る。それから最後に犠牲獣を屠り、神が自ら寄生木を授けた者たちに吉兆となる贈り物を与えてくれるように祈る。飲み物に入れた寄生木は不妊の動物を多産にし、あらゆる毒に効く解毒剤になると彼らは思っている。」
(プリニウス「博物誌」)
もうひとつ、蛇を崇拝するというイメージも根強い。
「ガリア属州には非常に名高いある種の卵がある。
蛇は多数絡み合い、喉から唾液を、体から泡を出し、不自然な交尾によってこのような卵を産む。それは「風の卵」と呼ばれる。
この卵は訴訟に勝ち、権力に近づく護符としてドルイドたちによって大いに讃えられている。」
(プリニウス「博物誌」)
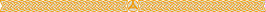
ケルト世界では水は異界に由来すると考えられていたようだ。
聖なる泉や井戸、河、湖には女神がいて「病気治療」への信仰が厚かったという。
水によって浄化されるという観念。
夜中に河で死ぬ人の血に染まった服を泣きながら洗うという妖精もいる。
これは再び生まれ変われるようにということなのだろうか?
湧き出て溢れ、そしてまた雨となり地に戻る。
水は再生のための聖なる物質であった。
ケルトではキリスト教のように超越的な力はこの世に最初からあるとは考えられていない。
それは異界からやってきて、また異界へと戻ってゆくもの。
何者も定着などしない。
常に変容し、活性化することを願う。
そのことを如実に表したのが、目に見える形で残した数々の美術・芸術品である。
あれは彼らの言葉だったのだろうか?
文字で残すことをしなかった者たちの雄弁な言葉。
妖しく複雑かと思えばシンプルな法則のもと、すべてを取り込もうと
すみずみにまで伸ばされた触手があらゆるものと同化してゆく、美しい言葉。
枠にはめられた途端に死んでしまうしかないと知っていたかのように。
先史時代の心を受け継ぎ、ケルトはまたその世界観を誰に伝えたのだろう?
かつて画家・大野忠夫はその著作「かみ・ひと・かたち」の中で書いている。
「形は心のあらわれであり、心とはまた彼らの生活様式であるといってもよいし、
世界観と言ってもよいだろう。形が似るということは心が似ていることなのだ」と。
ケルトが惹かれ導き出した「かたち」を、同じように生み出せる人がいる。
今も、これからも。
普遍性と自由(変化)を両立させようとする試み。
それは決して「すべて」の人の賛同を得るものではないかもしれない。
あるいはどうしようもなく迫害を受けることさえあるかもしれない。
ただそれを求める人というのはどうしようもなく「深く、理屈ではないところで」
惹かれるだろう。
強烈に。
似ているのは「こころ」なのだから。
|