|
西海岸最大の都市ゴルウェイからアラン諸島・イニシモア島に向かったときのこと。
1日1往復するというその船は何組もの団体観光客で賑わっていた。
私の目的といえばおそらくその大勢と同じく、島の南西部にあるダン・エンガスの古代遺跡。
そのちょうど反対側にあるキルローナンという小さな港にはバンや小型バスが大挙して待っていた。
乗り合わせた一台のバスの中で乗客のひとりがドライバーに「ゲール語(アイルランド語)を
話せるか?」と聞いていた。
彼はすぐさま聞き慣れない英語とは明らかに違う言葉を話し始めた。
ゲール語でなくとも、アイルランド各地で出会った地元の人の中にはたしかに英語であるのに
分からない「アイルランド訛」を話す人もいて、それはただでさえノーマルスピードの英語に
四苦八苦している身にはほとんどお手上げ状態だった。
たとえれば何とはなしに「音楽のような」フワフワとした発音である。
イニシモア島で出会ったゲール語もまたそうであったように思う。
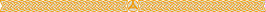
英国による本格的なアイルランド征服が行われたのは16世紀以降のことといわれている。
それまでにもノルマン人は侵入してきていたのだが、
植民者である貴族たちはゲール文化を保護し、土着のアイルランド人と結婚することによって
ますます同化してゆく傾向にあったという。
それに対して1366年キルケニー法と呼ばれるゲール人との結婚やゲール語の使用を
禁止するものが制定されたが、これは一種の「隔離政策」であり弾圧にまでは及ばなかったらしい。
それがイングランドでバラ戦争が終結した頃より方針は一転され、
ゲール文化自体を一切否定する方向へと切り替わった。
まずヘンリー8世による宗教革命をアイルランドでも行う。
カトリック(アイルランド人)は追放され、英国本土から大量のプロテスタントが入植してきた。
いくつかの反乱はあったもののアイルランドの英国化は押し進められていった。
この間、英国内部でもピューリタン革命期にプロテスタント派とカトリック派による戦乱が続き、
それにアイルランドも巻き込まれた形でカトリックすなわちアイルランド人は
宗教と言語による弾圧が強められ、おりからの大飢饉による打撃と共に国家を揺るがせた。
その中でオコンネルやパーネルら英雄的指導者のもと、カトリックの解放・土地問題など
徐々に復興、ついに第二次大戦後アイルランドは共和国として英国連邦から独立する。が…
自由国成立時にもこれに加わらず英国領として留まることとなった北アイルランドともうひとつ、
回復しなかった問題がある。
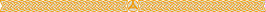
英国の徹底的な言語弾圧は、世界的な経済情勢の方向性として国民自ら「英語」の重要性を認め、
母国語を駆逐してしまったのだ。
現在、日常的にゲール語を使用する(ゲールタハト)のはもはや西部地方の一部に限られている。
アイルランド人にとって英国は心底忌むべき存在でありながら、その国の言葉を
受け入れずにはいられなかった。
言語というのはその国、ひいてはそこに生活する人間(思考)そのものであるはずなのに、だ。
この点、経済基盤の奇蹟の復興を遂げた日本および日本語と比較してみると興味深い。
大戦中、入植地に強要したのは日本(語)の方だが、
敗北するにあたって多少アメリカナイズされた部分があるものの、伝統文化、
とりわけ日本語が蔑ろにされることは一度とてなかった。
いま、ケルトブームに乗ってアイルランドのサブカルチャーが世界へ向けて発信されているが、
それが「英語」でなかったなら一種のローカル文化のひとつとして片付けられていたのではないか?
実際のところ「ゲール語」で歌われる現代ポップスもありそれなりに注目を集めているが、
世界に発信するにはその共通言語である「英語」が圧倒的有利であることは否めない。
ま、「世界的ヒット」というのがすなわち「アメリカで認められること」とイコールなのが
現状であると言われればそれまでなのだが。
ともあれ日常語として「英語」が蔓延してしまったからには、
その汎用性の中でこれからもケルト文化は邁進してゆくのだろうし、
日本は日本語でその文化を語ってゆくのだろう。
経済力と文化、そして言語の力というものにおいても、この東西の島国は好対照をなしている
20世紀末である。
|